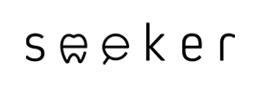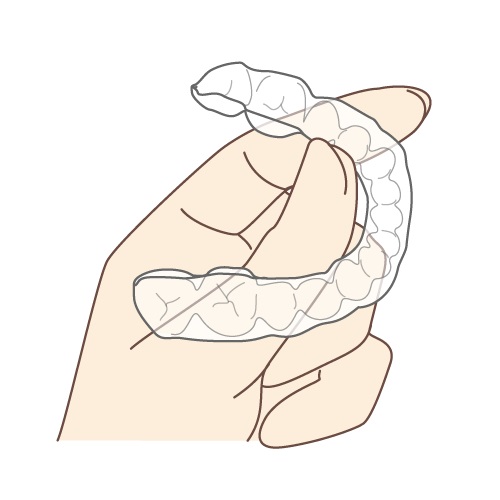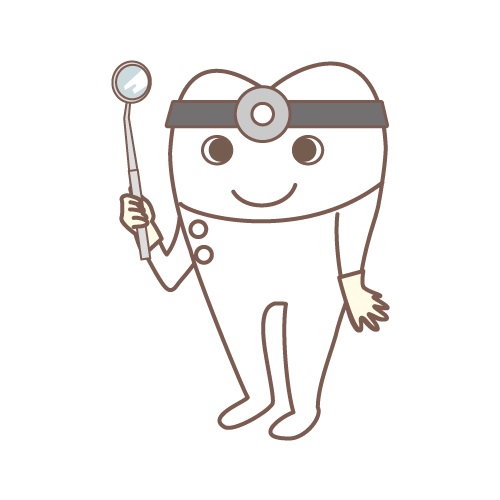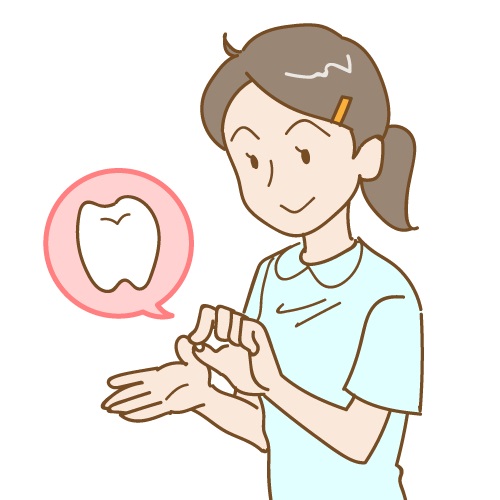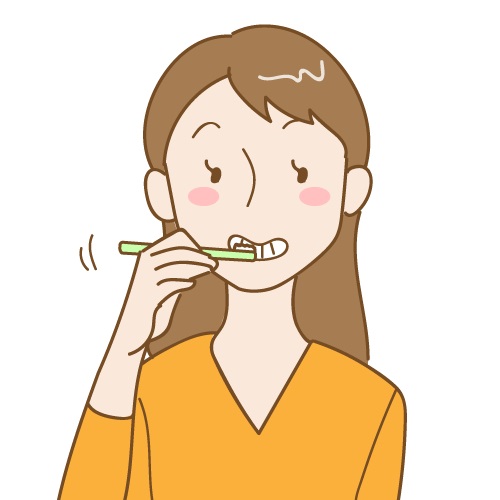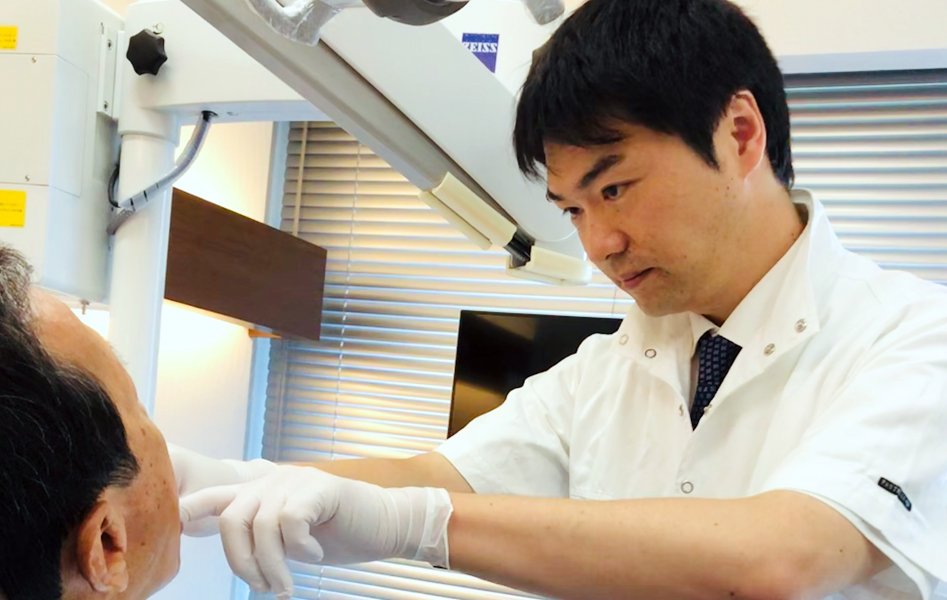コラム>歯の豆知識
2022/09/20
口元の老化を防ぐ? 噛むことと健康の関係とは

しっかりと食べ物を噛むことは口周りの筋力アップだけでなく、だ液の分泌量にも影響を与えます。 また、だ液は胃の働きを助ける以外にも、脳の活性化といったさまざまな効果があることから、噛むことは口元の老化や健康と深いかかわりがあります。老化とともに咀嚼回数やだ液の分泌量が減少しやすいといわれることからも、年齢を重ねるほど噛むことを意識して食事を摂ることが健康につながります。 今回は、噛むことと健康と深い関係について見ていきましょう。
噛むことと健康の関係
食べ物をよく噛むことは、ただ単に食べ物を飲み込むための作業ではありません。噛むことは食べ物を飲み込みやすくなるだけでなく、健康に関わるさまざまな効果があります。詳しく見ていきましょう。
顔周りの筋力アップ
顔には表情筋や咬筋といったさまざまな筋肉が集まっています。噛む回数が増えるほど顔周りの筋肉を鍛えられるため、脂肪燃焼やリフトアップ効果が期待できるでしょう。 また、しっかりと噛んで食べることはあごの発達にも関わるため、歯並びや噛み合わせにも影響するといわれています。顔周りの筋力や歯並びは、言葉の発音にも影響するため、食べ物をよく噛む習慣があることはとても大切です。
胃の働きを助ける
食べ物をよく噛むことで、だ液の分泌が活発になります。だ液には消化酵素が含まれているため、食べ物とよく混ざることで消化が進み、胃腸への負担を和らげてくれる効果が期待できます。 食べ物をよく噛まずに飲み込んでしまうと、本来、だ液によって消化が進むはずだったものが、そのまま胃へ流れてしまいます。胃は必要以上に働かなければならないため、胃の負担が増えてしまうでしょう。

歯の病気予防、だ液の分泌量アップ
よく噛むことは、だ液が十分に分泌される効果があります。十分な量のだ液が分泌されると、口に残った食べ物の残りかすなどが胃へ流れやすくなるため、口腔内を清潔に保ちやすいです。だ液自体にはこのような自浄作用もあります。 虫歯菌とたたかうペルオキシダーゼという酵素がだ液には含まれており、歯周病菌や虫歯菌が口腔内に増えるのを抑える作用が期待されます。そのため、虫歯や歯周病、口内炎などの予防につながるでしょう。 さらに、だ液には虫歯菌が作り出す酸を中和したり、歯の再石灰化を促したりする作用もあるため、歯の健康のために重要な働きを担っています。
脳の機能向上
食べ物をよく噛むことで、脳が刺激され、脳機能が向上するといわれています。理由は、噛むことの刺激によって、大脳皮質の感覚野や運動野、小脳、視床などが活性化されるからです。 歯と歯が噛みあう感覚や味覚といった情報が視床を経由して各部位に届けられ、運動をコントロールする運動野や小脳などが活性化され、咀嚼へとつながります。 また、口のなかは、小さなごみが入っても気が付くほど鋭い感覚を持っています。噛むことでさまざまな刺激が脳に伝わり、感覚系や運動系の部位が刺激され脳が活性化します。
肥満予防、栄養バランスがよくなる
食べ物をよく噛むことで、肥満予防の効果も期待されています。ゆっくりとよく噛んで食べることで、脳の満腹中枢が刺激されるためです。よく噛むことは、少ない量で食事の満足感を得やすいため、肥満予防につながるでしょう。 また、噛む習慣がないと、噛まなくても食べられる柔らかいものを好むようになりがちです。そのため、栄養バランスが悪くなる可能性もあるでしょう。特に、食物繊維を多く含む食べ物は、よく噛むことが大切です。食物繊維を摂る量が極端に少ないと、便秘などになりやすくなることがあります。

入れ歯は噛む力が3分の1に
食べ物をよく噛むためには、健康な歯が必要です。しかし、虫歯や歯周病などによって歯を失った場合、入れ歯を使用するケースもあるでしょう。入れ歯の噛む力は、健康な歯の噛む力の3分の1程度になるといわれています。そのため、今まで食べることができた物が食べられなくなる可能性もあるでしょう。 また、プラスチックで作られた入れ歯は、食べ物の熱い・冷たいといった感覚が伝わりにくい傾向にあります。そのため、レジンのみで作った入れ歯は、食べ物のおいしさや味の感じ方が健康な歯を使用した時と異なるでしょう。 また、レジンのみで作った入れ歯は厚みがあるため、使用すると口の中に異物感があります。入れ歯に慣れるまで、会話がしにくいと感じるかもしれません。

噛む力を鍛えて健康維持を
健康な歯を失い、入れ歯を使用するようになると、今までとは異なる食生活になるかもしれません。まずは、食事をするときはしっかりとよく噛むことが大切です。だ液を分泌させ、口周りの筋肉をしっかりと動かしましょう。加えて、毎日のセルフケアを丁寧に行い、定期検診を受けることが大切です。
筆者:seeker編集部