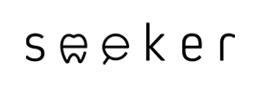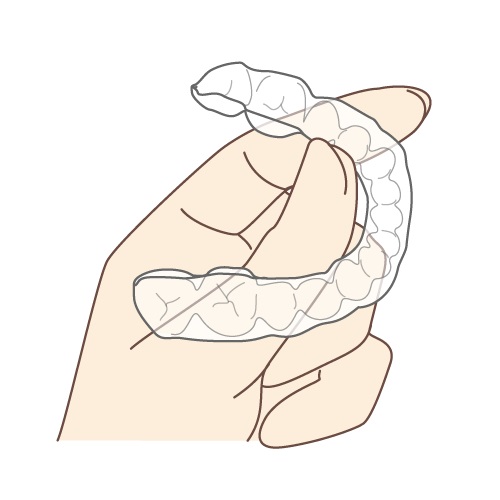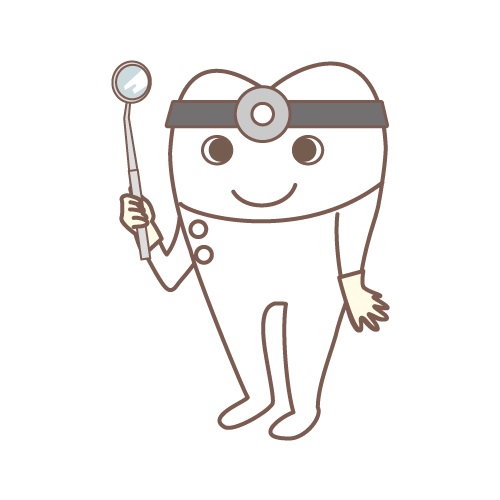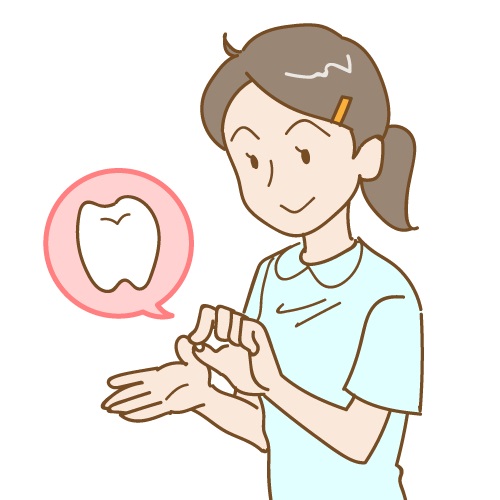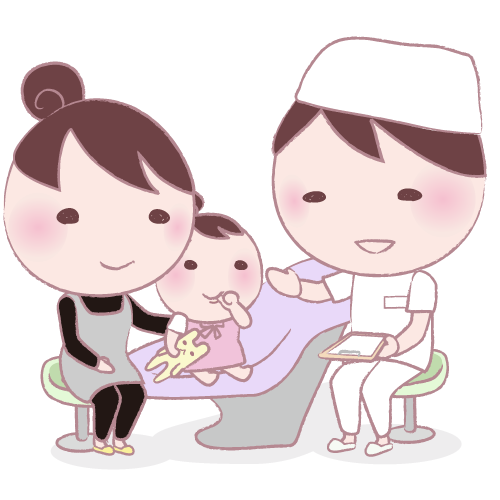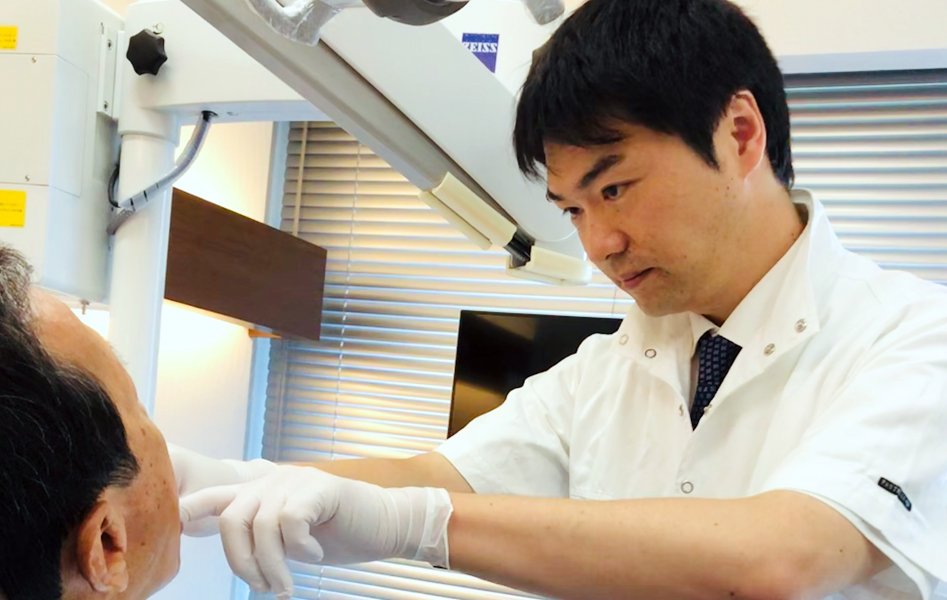コラム>小児歯科
2022/06/24
乳幼児の食事は一生の味覚を左右するって本当!?子育てと食育
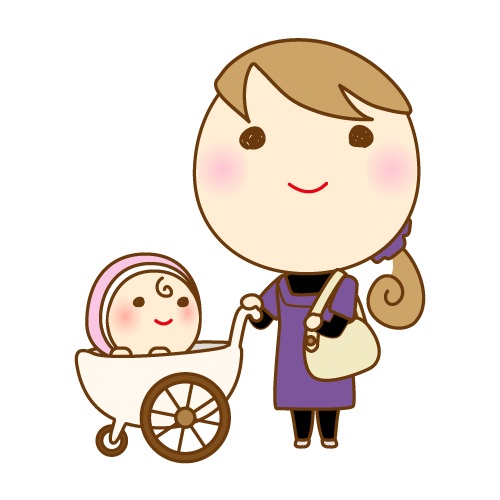
乳幼児の食事は一生の味覚を左右するといっても過言ではありません。味覚はお口の健康とも関係しており、甘味ばかりを欲しがるようになるとむし歯のリスクが高まります。 また、味覚を育てるために必要な「よく噛むこと」も、健康なお口を維持するために重要なことです。今回のコラムでは、味覚の育て方についてお話します。
5つの味覚と役割
味覚は、甘味・塩味・うま味・酸味・苦味の5つに分類されます。まず、それぞれの役割をみてみましょう。
甘味・塩味・うま味は、生きていくために必要な食べ物が含む味なので、本能的に好まれる味とされ「おいしい」と感じます。一方、酸味と苦味は生きるために避けるべき「危険な食べ物」を伝える役割を持つため、初めは受け入れられず「まずい」と感じます。 このように5つの味覚によって、人は「口に入れても安全か」「身体に必要か」を判断しているのです。
子どもの味覚形成
味覚が最も敏感なのは、生まれてから3ヶ月くらいまでといわれており、5ヶ月を過ぎた頃から少しずつ鈍感になっていきます。母乳の味に少しでも変化があると、赤ちゃんが嫌がって飲まなくなるのは、この敏感さゆえのものです。 また、大人になって、子供の頃に食べられなかったものをおいしいと感じるのも、幼い時ほど味覚が繊細でないためといわれています。食べ物をお口の中に留めて舌で感じたりよく噛んだりすることは、味覚を発達させます。 また、小さい頃からさまざまな味をインプットしておくことも大切です。次章から、味覚を育てるために注意すべきことやおさえておきたいポイントについてお伝えします。
こんな食事は要注意!
調味料の使い過ぎ
調味料の味は素材本来の味を隠してしまうので、使い過ぎることのないようにしましょう。調味料に慣れてしまうと、成長しても濃い味を好むようになります。素材の味を楽しむことができず、濃い味を好むようになると、内臓に負担がかかってしまいます。
食事に嫌な思い出を結びつけない
成長するにつれ、味だけでなく環境や身体の状態など、あらゆる情報に紐づいて食べ物の好き嫌いを判断するようになります。無理やり口に入れられた、体調が悪い時に食べた、などをきっかけに嫌いになることや、その反面、友達と一緒に食べた、幼稚園で育てたなどの経験が伴うと、途端に好きになることも少なくありません。 記憶による影響を受けやすい幼少期は、楽しい思い出と共に食事をするように心がけましょう。
砂糖の摂り過ぎ
前述したように、甘みは乳幼児が好む味です。特に気をつけたいのが砂糖の摂り過ぎです。喜ぶから、機嫌がよくなるからといって、つい与え過ぎてしまうことがありますが、むし歯菌のえさである砂糖を取り過ぎてしまうと、むし歯になるリスクが高くなります。 砂糖の摂取は控え、甘味の摂取はりんごやバナナなどのフルーツ、さつまいもやとうもろこしなどの野菜、レーズンなどのドライフルーツから摂るようにしましょう。
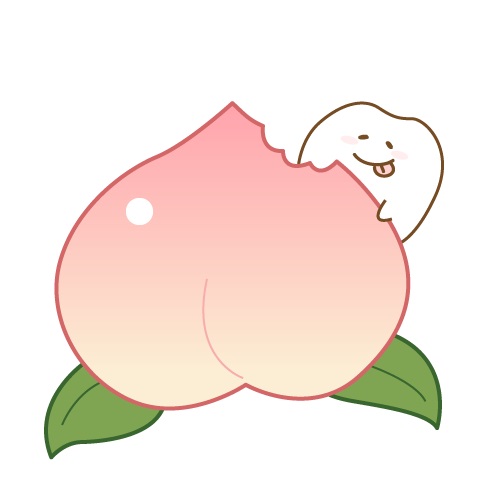
子どもの味覚を育てる3つのポイント
1.たくさんの食を経験させる
乳幼児の頃からたくさんの食材の味に親しむことが大切です。旬の食材をはじめ、たくさんの食材に触れる機会を持ちましょう。子どもの味覚形成には、見た目や色、形状、香り、舌触り、食べる環境などさまざまな要素が関係しています。味以外の要素にも工夫をした食事作りを心がけましょう。
2.食事を楽しいと感じる環境づくり
テレビやスマホをみながらの食事や孤食をさせていると、食に楽しさを感じられなくなります。家族全員で食卓を囲み、「食べる」ことに集中し、楽しみを見出せるようにしましょう。食事の時間を十分に取り、よく噛んで食べる習慣を身につけることも大切です。
3.おやつの選び方に注意
おやつというとチョコレートなどのお菓子をイメージしますが、乳幼児のおやつは「補食」を意味します。乳幼児期は成長や発達のために多くの栄養素を必要としますが、胃や消化器官が未熟なので、1日3回の食事で必要な栄養素を摂取しようとすると、身体に大きな負担をかけてしまいます。そこで、おやつを食べることで必要な栄養素を効率よく摂取します。 おやつを選ぶ時は、小魚や昆布、おにぎり、フルーツ、芋類や豆類など、足りない栄養素を補うことを意識しましょう。

▶子供のおやつに関してはこちらのコラムで詳しく解説しています。本コラムとあわせてご覧ください。 子供の歯を守りたい!おやつをあげてはいけないの?
乳幼児期の食事が一生の味覚をつかさどることは間違いありません。また乳幼児期の食事によってむし歯のリスクは低くなります。味覚もお口の健康も、一生に関わるものなので、しっかり備えておきたいですね。
筆者:seeker編集部